仕事で失敗をしたことで、自信を失ったり、上司や同僚から叱られたりしたことは誰しもが経験したことがあるでしょう。
また、失敗の内容によっては損害賠償や減給などの不利益を被ってしまうことも…。仕事の失敗は誰にでも起こりうることですが、その影響は大きく、辞めたいと思うほどストレスや不安になることもあります。
私も一時期、うっかりミスを連発して、「自分はもしかすると認知症でも発症してしまったんじゃないか」なんて悩んだ時期がありました。そのとき「スマホ認知症」なんて言葉も流行っていた時期ですから余計ですね。
この記事では、仕事の失敗が多くて辞めたいと思っている人に向けて、ミスの原因やミスの分類法と予防法、体験談などを分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、あなたは仕事のミスに対して前向きになれるでしょう。ミスや失敗から学ぶことは多いものです。ミスをしたらミスを分析して次同じミスをしないようにすればいいんです。
この記事の結論は以下の通りです。
- ミスの原因には①心理的要因と②環境的要因の2つがあり、それらが複雑に絡み合ってミスが起こる。
- それらのミスは①スリップ(うっかりしてて間違いました)、②ラプス(うっかりしてて忘れちゃいました)、③ミステイク(こうするんだと思い込んでました)、④バイオレーション(こっちの方がいいと思いました)の4つに分類できる。
- それぞれのミスが起こらないようにするには、周囲の状況を整えたり、教育が必要だったり4つのミスの分類によって対処法が異なる。
- もしミスが起こってしまったら、まずは冷静に状況を把握し、上司に報告、謝罪し、対応策を講じることが必須となる。隠したり、言い訳をしても良い結果にはならないことがほとんど。
- ミスを分類し、分析して次に同じことが起こらないよう分類に基づく改善を行う必要がある。
- ミスは成功への第一歩。ミスから学んで成長につなげる姿勢を忘れないことが大切。
仕事のミスの原因
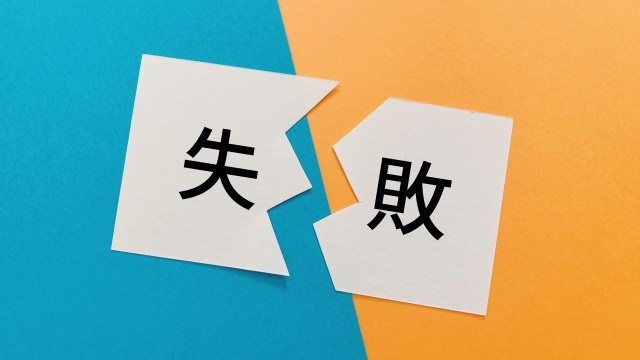
仕事のミスは様々な原因で起こりますが、ミスは主に2つの要因が複雑に絡み合っています。その2つの要因とは、①心理的要因、②環境的要因です。
心理的要因
心理的要因は、自分の気持ちや考え方がミスに影響することです。例えば、以下のような場合があります。
- ストレスや疲労が溜まっている場合。集中力や注意力が低下し、ミスをしやすくなる。
- 自信がない場合。自分の判断や能力に不安を感じ、ミスを恐れて緊張しすぎたり、逆に無気力になったりする。
- 意欲や興味がない場合。仕事への責任感やモチベーションが低下し、ミスを放置したり改善しなかったりする。
- 感情的になる場合。怒りや悲しみなどの感情が判断力や行動力に影響し、冷静さを失ってミスをする。 など
環境的要因
環境的要因とは、自分以外の外部要素がミスに影響することです。例えば、以下のような場合があります。
- 情報量が多すぎたり、少なすぎたりする場合。必要な情報を見落としたり、誤解したりする。
- 時間や期限が厳しすぎる場合。慌てて作業を行い、ミスをしやすくなる。
- 職場の人間関係が悪い場合。相互のコミュニケーションが不十分になり、ミスの原因や結果に対する認識や対応がずれたり、トラブルになったりする。
- 業務の内容や手順が複雑すぎる場合。理解や実行が困難になり、ミスをしやすくなる。 など
これら2つの要因が複雑に絡み合ってミスは起こります。分かりにくいので具体例を出すと以下のような例でしょうか。
発注まで時間がなく、締め切りに追われてストレスがたまり、単価の値段や必要な商品を発注するという部分に気を取られています。そうすると、普段なら気づくはずの「発注個数」のような間違えてはいけない部分を間違えてしまう、と言ったところでしょうか。
(よくコンビニで「誤発注しちゃいました、てへっ!」ってやつですね。あれもそういう商法になっていたりして、信用ならないですが…)
以前はミスは「その人の性格や個人の問題だ」と言われてきましたが、現在はミスは「環境」「作業内容」「組織」などに原因があり、それらを調べる必要があることが分かってきたのです。(心理的要因についてもそれを軽減する方法が組織になかったということ)
人間はミスをする生き物です。誤発注の例では、例えば普段と違う発注個数が注文されたとき、アラートで教えるという機能が加えられていれば、ミスが防げたかもしれません。
そういった意味で、ミスを分析して発生のメカニズムを解明しておくことが、次につながるまさに「失敗学」になるわけです。
仕事のミスの分類方法と事前防止

起こったミスを分析して、次に生かすためには、まずはそのミスがどのようなミスだったのか分類する必要があります。
ミスの分類
一般的に、人間が起こすミスのことをヒューマンエラーと呼びますが、ヒューマンエラーは①スリップ(slip)、②ラプス(lapse)、③ミステイク(mistake)、そして④バイオレーション(violation)の4つに分類されます(J.Reoson氏の分類)。
| ミスの種類 | 内容 | 例 | 事前防止 |
| スリップ | 意図した内容と違うことをしてしまう(無意図的)。 | Aというボタンを押そうとしたら、Bというボタンを押してしまった。 | 指差し確認などをして確認をするようにする。 |
| ラプス | 意図した内容を忘れてしまう。度忘れ。 | Aというボタンを押そうとしたら、横から話しかけられて押すのを忘れてしまった。 | メモを取ったり、タイマーを使ったりする。 |
| ミステイク | 意図を計画する時点ですでに間違っている。 | Aというボタンを押さなければならないのに、最初からBを押すことが正解となっていた。 | マニュアルの改訂や教育、訓練をする。 |
| バイオレーション | 意図的にルール・規則を破ってしまう。 | Aというボタンを押さなければならないと計画でもなっているのに、あえてBのボタンを押した。 | 環境を整える、正しい手順を訓練する、小さな違反を見逃さない。 |
スリップやラプスは人間の判断ミスによって起こるもので、「うっかりしてました」などのミスがこれにあたります。
ミステイクは知識や経験の不足によって起こるものです。「こうするんだと思い込んでました」がこれにあたります。
バイオレーションはルール・規則を破ることによって利益が得られるときによく起こります。「こっちの方がいいと思ったので」がこのミスです。
もしミスが起こった場合は、どれに分類できるかを考え、その対処法を考えていくことが重要です。
ミスの事前防止方法
まずはこれらのヒューマンエラー、ミスを無くすための事前防止法について述べていきます。もしミスをしやすいなぁと感じる場合、まずは以下の事前防止法をしっかりと行って、ミスの少ない心理的・環境的要因を作っていくことが大切です。
スリップ——「うっかりして間違いました」を無くす方法
スリップは作業環境や機器の配置によってよく起こります。また、注意力や集中力が低下したときにも起こりやすいミスですので、それらを排除してあげることが重要になります。具体的には以下にあげるような方法です。
- 作業環境を整理整頓し、必要なものだけを手元に置く。
- 機器や道具の配置を工夫し、間違えやすいものは離して置く。
- 作業前に目的や手順を確認し、作業中に自分の動作を声に出して確認する。
- 作業後に結果や内容をチェックし、誤りがないか確認する。
病院で薬の取り違えなどが起こらないように、1人ではなく2人のダブルチェックを行うのはこのためですね。
ラプス——「うっかりして忘れてしまいました」を無くす方法
ラプスは情報量が多すぎたり、記憶や判断の誤りなので、似たようなものがあったりすると起こりやすくなります。
- 情報を整理し、今の作業に必要なものだけを覚えるようにする。
- 似たようなものは区別しやすいようにする。
- メモやリストを活用し、忘れやすいものは書き留める、スマホのリマインダーなどを活用する。
- 確認事項やチェックポイントを設定し、漏れがないか確認する。
電車の運転士さんが指差し確認をしながら信号機の状況を確認するのは、この「うっかりして見逃しました」を無くすための方法なのですね。
ミステイク——「こうするんだと思い込んでました」を無くす方法
ミステイクは知識や技能の不足によって起こる、と書くと新人さんが起こすミスのように見えますが、実はベテランにも起こりうるミスです。同じやり方を違う場所でもやってみたらミスった、なんてのはベテランさんによく起こるミスです。
- 知識や技能を定期的に学習して新しい内容に更新し、レベルアップしていく。
- 分からないことは素直に聞き、指示や受け入れる。
- ルールやマニュアルを明確化し、共有する。
- フィードバックや評価を行い、改善点や成長点を把握する。
バイオレーション——「こっちの方がいいと思いました」を無くす方法
バイオレーションは自分の都合や利益を優先したり、ルールや規則に納得していないときに起こりやすくなります。
- ルールや規則の意義を理解し、遵守する。
- ルールや規則に不満や疑問があれば、適切な方法で提案や改善を行う。
- ルールや規則の違反に対しては、小さなことでも見逃さず、厳正に対処する(割れ窓理論)
- ルールや規則の遵守に対しては、適切に評価する。
また、これらの事前防止法以外にも、①睡眠をしっかりととる、②最低でも90分に1回は休憩を取って集中力を回復させる、③コミュニケーションを取ってお互いにカバーし合う、などの方法が考えられます。
仕事でミスが起こってしまったら——ミスへの対処法

どれだけ注意していても、誰しもミスはしてしまうもの。もしミスが起こってしまったときは、以下のような対応を取ることが大切です。
ミスに気づいたら、まずは落ち着いてミスの状況を確認します。決してパニックになたりせず、否定したり隠したりしないようにしましょう。ミスは誰にでも起こりえることですから、自分を責めすぎずに。
ミスの種類や程度、原因やどのような影響があるかを確認し、関係者や被害者を洗い出します。それらを上司に報告し、指示を仰ぐなどします。この上司への報告が遅れると、かえって状況を悪化させてしまうことがあるので、早めに報告を入れるようにした方が賢明です。
ミスの影響を最小限に抑えるために、できるだけ素早く行動します。自分でできることは自分で行い、自分だけでできないことは同僚や上司に協力・助言を求めます。
ミスの種類や程度に応じて、適切な方法で修正や訂正を行います。例えば、書類の打ち間違いなどは再印刷できるのであれば速やかに修正したものを印刷したり、間に合わないのであれば赤ペン等で修正をかけたりします。
メールの誤送信などでは、素早く訂正メールを送るなどします。
この対策や対応はスピード勝負になることも多いので、急いで対応することが大切です。
いくらミスは個人の責任だけとは言えなくなってきている、とは言っても、ミスをしてしまったのは自分です。ミスや状況に応じて上司やクライアントに謝罪をします。謝罪をするときには以下の点に気を付けましょう。
- 謝罪は早めに行います。遅れれば遅れるだけ信用を失います。STEP3の対応を進める前の段階と、対応策がある程度進んで、被害の拡大が防げた段階で、誠心誠意謝罪することが大切です。
- 謝罪はできるだけ対面で行います。被害の状況にもよりますが、電話やメールのみでの対応は相手に不親切だと取られかねません。
- 謝罪は具体的に行います。ミスの内容や影響、対応策について明確に伝えます。
- 謝罪は軽く行いません。「すみません」や「申し訳ありません」だけでは不十分です。相手の気持ちに寄り添って、謝罪することが大切です。
- ミスの内容によっては、補償や賠償を行う必要がでます。過剰でも不足でもなく、相手が納得できる範囲で行うこともあります。
上司や同僚から𠮟責を受けるかもしれませんが、それは甘んじて受け入れましょう。それらはあなたの成長につながる貴重なフィードバックにです。
フィードバックを受ける際には、反論したり言い訳をせず、素直に受け入れることが大切です。相手の言葉に耳を傾け、感謝の示しましょう。
また、ミスの分類を行い、何が原因で起こったのかを分析し、次に同じことが起こらないよう環境や組織の改善・修正を行います。
仕事のミスの体験談

体験談① 発注ミスをしてしまい…30代男性
仕事で必要な備品を発注することになり、FAXで注文。後日、届いた備品は必要な量の10倍!しかもそれを上司に報告せず隠していたもんだから、それはそれは大目玉をくらいました。
やはりミスをしてしまったら、正直に隠さず報告しなければいけないなって学びました。
(これは典型的なスリップの例ですね。個数を指差し確認する、他の人にも確認してもらう、などをすれば防げたミスです)
体験談② 大事な機械を…20代男性
工場で作業員として勤務していたときのこと。部品を切断するためのカッターを新調し、2週間ほど経ったときのこと。
それまで正確に切れていた機械に不具合が出て、おかしいなと見てみるとカッターの近くに自分が使ったハンマーが。
どうやら、何かの作業をしたあと、誤って刃が下りてくる周囲に自分が置き忘れてしまい、刃に触れて壊れていました。
すぐ上長に報告して事なきを得ましたが、自分でも置き忘れた記憶がないので、本当に気を付けなくてはいけないなと思いました。(修理代は結構高くついたようです…)
(これはラプスの例です。ハンバーの置き場をうっかりして置いてはいけないところに置いてしまった、というミスです。これは、ハンマーを使ったら元の位置に戻す習慣をつけたり、道具がちゃんとしまわれているかを終業前に確認する、ということをすればよかったですね)
体験談③ 道に迷って…30代女性
あまり地図を読んだりするのが元々苦手だったんですが、仕事でお使いを頼まれました。住所と簡単な手書き地図をもらって、社用車で出かけました。
当時、その社用車にはカーナビなんてものはついておらず、道に迷って迷って、上司に電話で聞くのも恥ずかしくて、結局その場所に着けずに帰りました。
人を待たせているという類のお使いではなかったのでよかったですが、上司にはあきれられてしまい、それからこういったお使い系のお仕事は振られなくなりました(笑)
(これはミステイクの例です。自分ではこの地図と住所で「行けるもんだ」と思っていたけど、実際は違ったという例です。これは素直に上司に道に迷ったことを伝え、道順を尋ねたり、初めからもっと詳しい地図で確認をすることによって防げたミスです)
体験談④ 一歩間違ったら…20代女性
看護師として働いて3年目、ようやく少しずつ独り立ちできて看護師の仕事に自信を持ち始めていたころ。
点滴の準備をして、ラインにつないで、点滴を落とすスピードを調節してその場を離れました。
本来であれば、点滴を落とすスピードを途中で調整する必要がある薬剤だったのですが、その日はとても忙しくてそのことを気に掛ける余裕がなく、気づけば点滴のスピードを変えなくてはいけない時間から1時間以上も経過していました。
真っ青になってその患者さんの元に行くと、特に変化はなく、先輩看護師から口頭で注意を受けるにとどまりましたが、もしこれで患者さんの容態に変化があったらと思うと血の気が引きました。
その後、わずかにあった自信も打ち砕かれ、落ち込んで仕事に手がつかない日が続きましたが、先輩看護師から飲みにさそってもらって吐き出させてもらって切り替えることができたのを覚えています。
(これはラプスの例です。忙しいという心理的要因によって、他の重要な仕事を忘れてしまうというのはよくあることです。これを防ぐには、タイマーをかけたり、別の看護師にもしっかりと申し送りをして気にかけてもらったりなど、組織全体でラプスが起こらないよう改善していかなければいけない事案ですね)
仕事のミスから学べること
仕事でミスをしたことは誰にでもあるはずです。しかし、ミスは決して無駄ではありません。ミスから学ぶことは多くあります。
- 自分の弱点や改善点を知る。
- 自分の能力や限界をしる。
- 自分の気持ちのありようや考え方のクセを見直す。
- 仕事の目的や意義を問い直す。
- 仕事の方法や手順を見直す。
- 仕事に対する責任感や姿勢を見直す。
- 仕事以外のバランスやリフレッシュ方法を見直す。
- 上司や同僚、お客様とのコミュニケーションや信頼関係を見直す。 など
ミスが起こったときには、これらを行うためのよい機会になります。ミスをしてしまったら、まずは自分の失敗を認めて、原因や影響を分析し、対処法や予防法を考えて実行しましょう。
そしてミスから学んだことを自分の成長につなげていくのです。ミスは成功への第一歩です。ミスを恐れずに、前向きに仕事に取り組みましょう。
仕事のミスが多くて辞めたい人へのまとめ
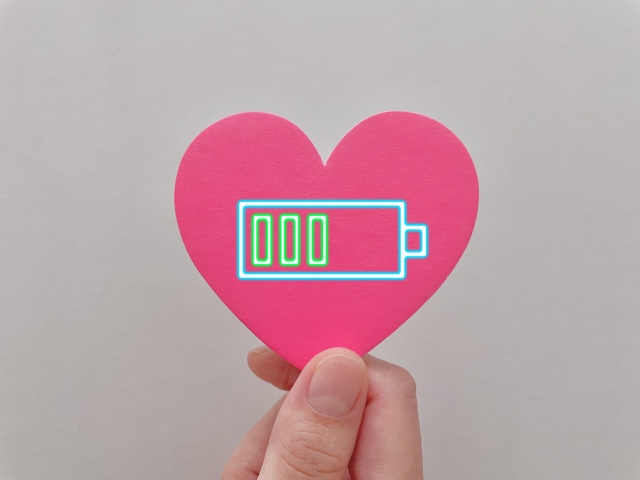
仕事のミスは決してあなた一人が悪いわけではありません。もちろん責任は取らなくてはいけませんが、そのミスから次に起こらないよう改善していく姿勢が大切になります。
上司や同僚の協力をもらいながら、組織を改善していくこともときに必要になるミスもあります。自分一人で抱え込まず、かつ、自分が改善できることは改善して次に進んでいく、それが仕事を行う上で大切な素養かもしれません。
辞める前に一度、今回起こったミスは何が原因で起こって、どのように改善すればよいか手段を考え、実行してみてはいかがでしょう?ふとした機会に成長した自分を実感できると思いますよ。

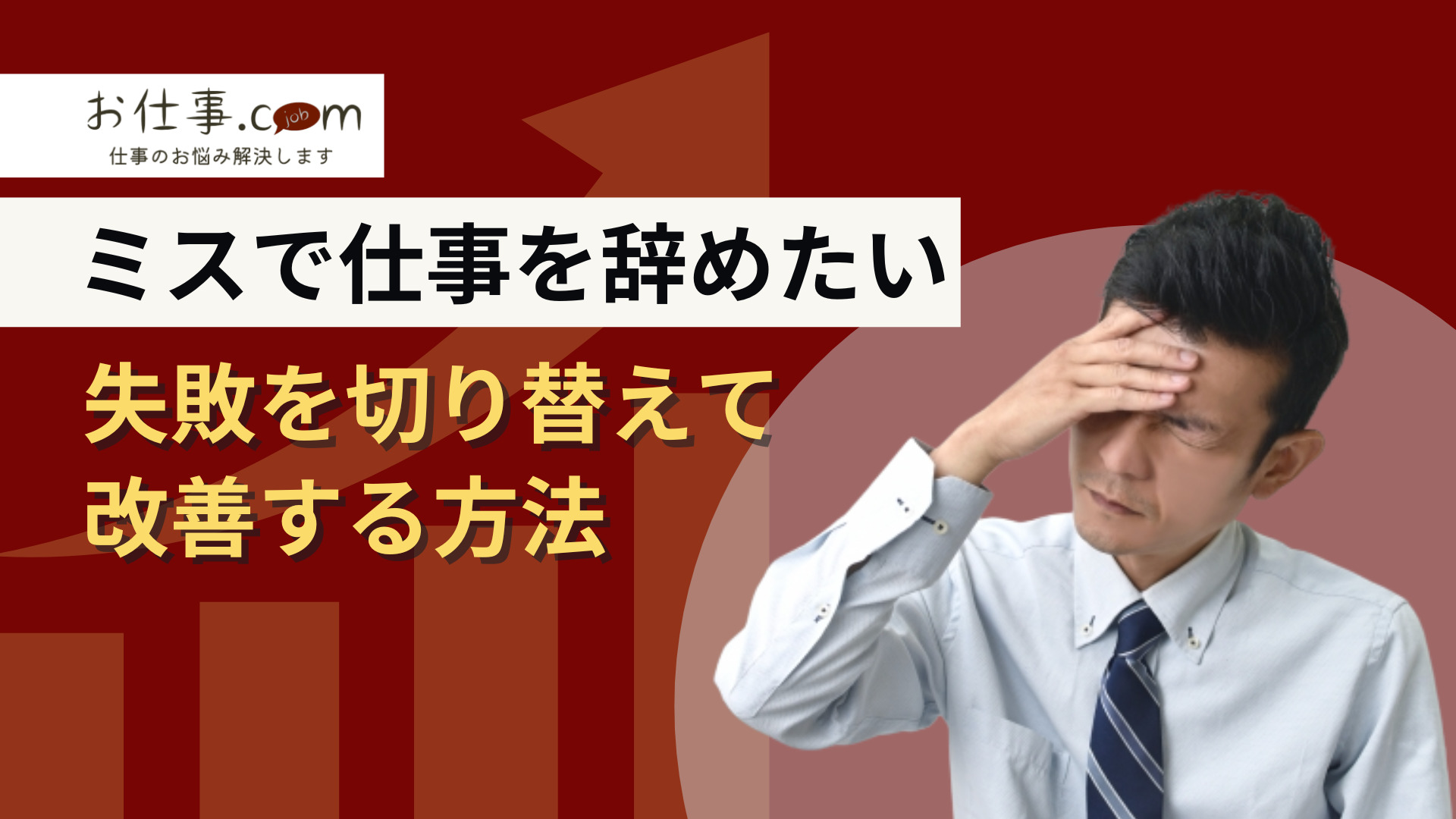


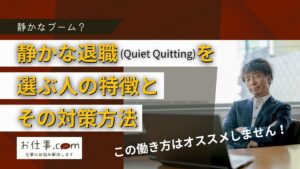
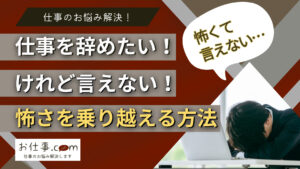

コメント